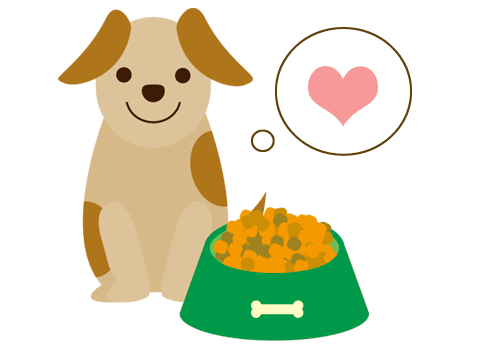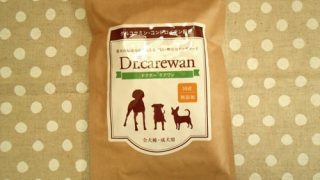「老犬には低タンパク食がよい」という話をあなたも耳にしたことはありませんか?
人間と同様、年を取れば体が必要とする栄養素は違ってくる…そう思えばごく自然なことなのかも?そう思ってしまいがちですが、実はこれは間違いです。
目次
シニアはいつから…?
一般的にシニアと呼ばれるのは、小型犬や中型犬で7才くらい、大型犬では5~6才くらいからと言われています。
まだまだその年齢を過ぎても元気なワンちゃんもいますが、やはり中には白髪が目立ってきたり、前よりも動きたがらなくなった…という“老化のサイン”が出てきている子もいるのではないでしょうか。
しかし、そこですぐに「シニア用のドッグフード」を選択するのはちょっと待ってください。
逆にその行為こそが、愛犬の老化を早めることになってしまうかもしれないのです。
シニア犬用フードで老化が加速する!?
メーカーによっては、「パピー・アダルト・シニア」と年齢別によってフードが分かれていることがあります。
パピーやアダルトなど多くのエネルギーを必要とする年齢では高タンパク高カロリーのドッグフードが多く、逆にシニア用となると低タンパクなもの(高炭水化物)がそのほとんどを占めているようです。
シニアには低タンパクが良いというのは、何となく分かる気はするけど詳しくは分からない…そんな方も多いでしょう。そこで、メーカーが話す「シニアには低タンパク」と言われる理由をご紹介します。
- 活発な若い成犬よりもたんぱく質を必要としない
- 低タンパク質のほうが老犬の腎臓保護に適している
- たんぱく質を炭水化物に変えることで肥満が予防できる
- 炭水化物はカロリーが低いうえ満腹感が得られる
一見「へぇ~そうなんだ」と納得してしまいますが、冒頭でも書いたようにこれは誤り。
なんと驚くことに「健康なシニア犬には健康な成犬の50%多くのたんぱく質が必要」という研究結果が出ているのです。
そう、シニア期を迎えた高齢のワンちゃんにも多くのたんぱく質が必要だったんです。まるで刷り込みのように「シニア犬には低タンパク」と言われていたので、それを信じていた方はびっくりされたのではないでしょうか。
たんぱく質の欠乏は筋肉の衰えを加速させ、免疫機能の低下からがんなどの大きな病気を招くと言われています。
「もう老犬だから…」という理由だけで低タンパク質のシニア用フードを与えることは、まだまだ元気でいられたワンちゃんを「老化」に導く危険な行為だったんです。
高タンパクの「高品質」なドッグフードを選ぶこと
高タンパクがいいと言っても、若い成犬の頃に比べるとシニアではたんぱく質の代謝機能が落ちているのはたしかです。ですので、大事なのは「質の良いたんぱく質」をしっかりと与えることです。
いくら高タンパクでも粗悪な肉原材料を使っていては意味がありませんからね。(これはシニアに限らずどの年齢のワンちゃんにも言えることですが…)
また、「低タンパク食=腎臓に良い」と言われていますが、全くそんなことはなく、消化の良い高品質なたんぱく質こそが腎臓に良いと外国の大学や研究機関でも証明されているそうです。
(ただ尿毒症など腎臓疾患がある場合は注意。自己判断せず、医師に相談することが必要です)
肝性脳症や末期の肝硬変に罹っている場合を除き、肝臓にも高品質なたんぱく質は良い働きが期待できます。
やはり、いくら年を取ってもワンちゃんの体には「たんぱく質」が絶対必要で無くてはならないものなんですね。
シニアにおすすめは高品質な高たんぱく・低炭水化物フード
どれだけ年を取っても愛しく愛くるしい愛犬。いつまでも元気でいてもらうには、適切な食事や運動、体重管理が欠かせません。
そんな中、シニアにおすすめの食事内容は「高品質な高たんぱく・低炭水化物食」と言えるでしょう。
世の中のシニア用ドッグフードの多くは、たんぱく質を抑え、その代わりに炭水化物を多くした高炭水化物フードです。
炭水化物のほうが動物性たんぱく質よりもコストが抑えられるのは明白ですから、「シニア用」と銘打ち、うまくシニア犬の飼い主さんをターゲットにするメーカーの戦略を感じずにはいられません…
最終的に判断するのは飼い主であるあなたですが、個人的にはシニアであっても「シニア犬用ドッグフード」はおすすめしません。(もちろん内容が良ければOK)
全年齢対応の高品質な高たんぱく・低炭水化物ドッグフードを愛犬の状態に合わせて量を調整して与えることをおすすめします。
結論:老犬も高タンパクフード(高品質なものに限る)がいい
低タンパク質のほうが老犬の体には優しそう…かくいう私もそう思っていた一人です。同じような方も多いのではないでしょうか。
年を取った愛犬の体のことを考えて選んでいた食事が、実は愛犬の老化を早め病気を助長していたなんてショックですよね。
やはりワンちゃんの食性には「たんぱく質」が欠かせない、ということを理解したうえで愛犬にぴったりのフードを選んであげてください。